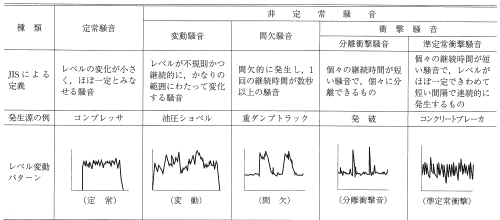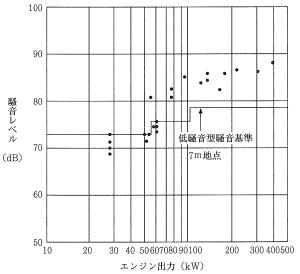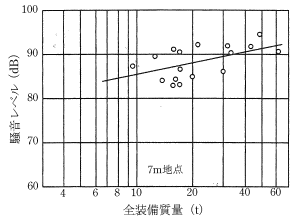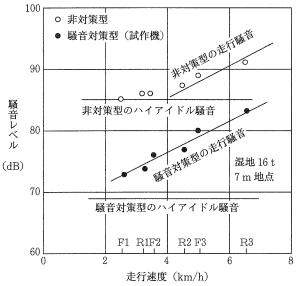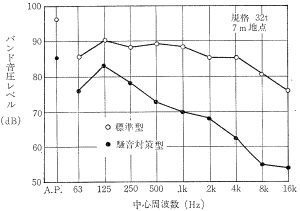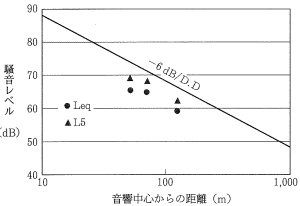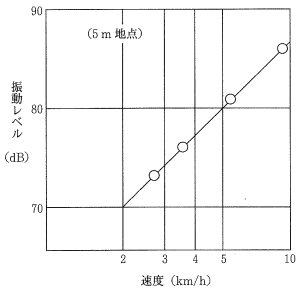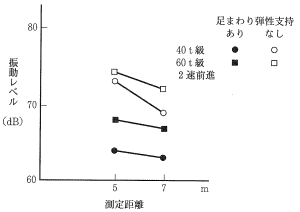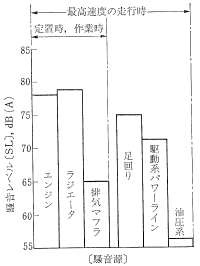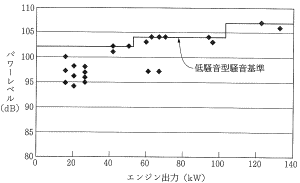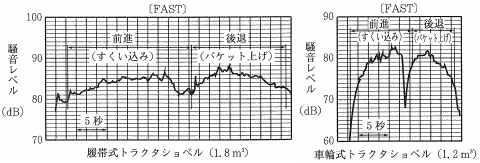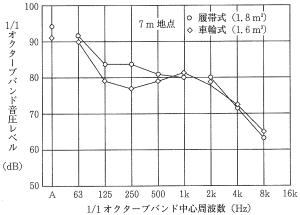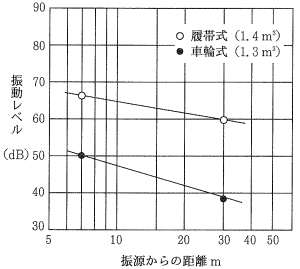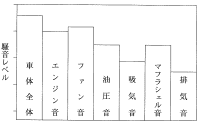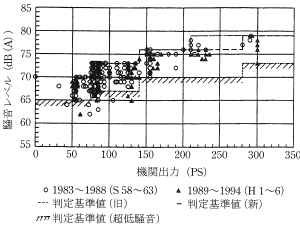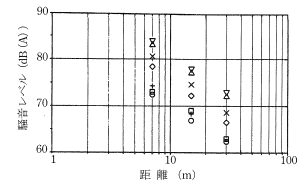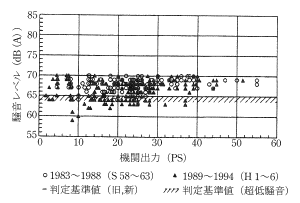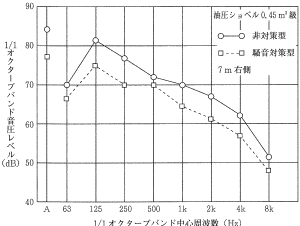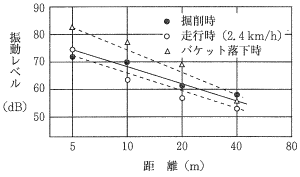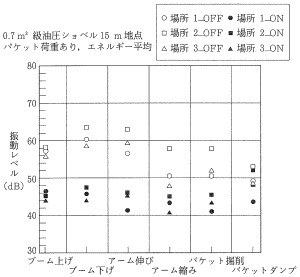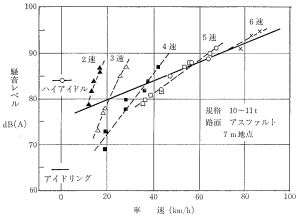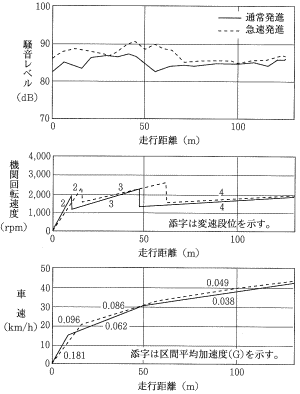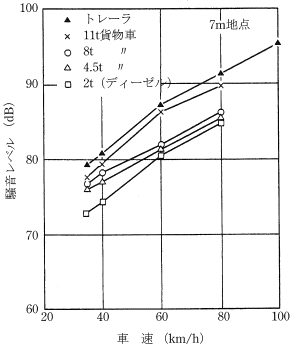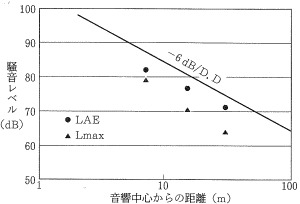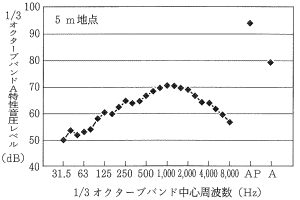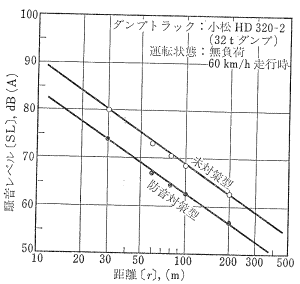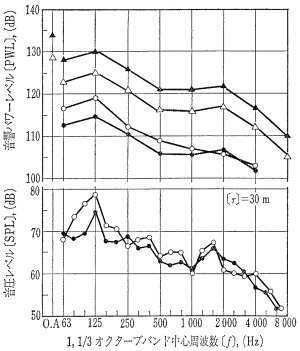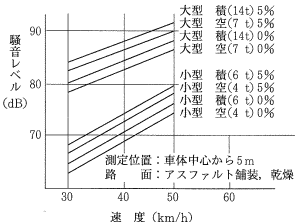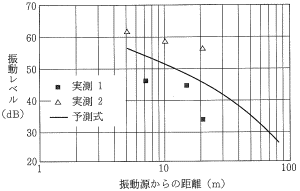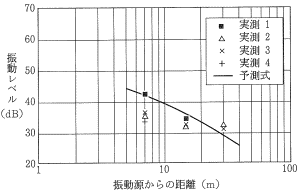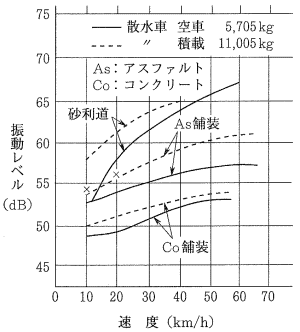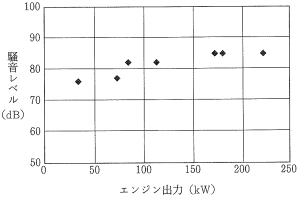- ローダ(トラクタショベル)
ローダ(トラクタショベル)は、タイヤ式のホィールローダとクローラ(履帯)式のトラックローダがあり、クローラタイプは振動・騒音がともに大きく、タイヤ式は振動が低い。
タイヤ式とクローラ式の機種選定は、地盤の走行性、機動性、足回り費用が大きな選択要素となっています。
ローダ作業は、ブルドーザ等で切崩した土砂・岩をダンプトラックに積込む作業で、前後進しながらバケット操作を行います。 積込法には、クロスローディングとVシフトローディングがあり、国内ではダンプトラックが共に動くクロスローディングが一般的です。
ローダの作業には、積込以外に小運搬的なロード&キャリがあります。
a) 騒 音
クローラ型のトラックローダ騒音は、ブルドーザと同様にエンジン騒音と足回りの走行音であり、ホィールローダの騒音はエンジン音とトルクコンバータ・ミッション系の音です。
積込時の積込材料に起因する音も岩・砂利等の場合は大きくなります。
図2-1は、ホィールローダのエンジン出力とパワーレベル(模擬作業時)の関係を示したもので、エンジン出力に比例してパワーレベルも増加しています。
|
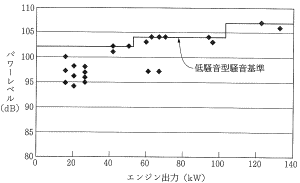
図2-1 ホィールローダのエンジン出力とパワーレベル(模擬作業時)
|
図2-2は、ローダ作業時の騒音レベル波形です。
図2-3は、ローダ作業の周波数特性(オクターブバンド)です。 履帯式の250Hz付近の卓越したスペクトルは、足回り騒音の影響と思われます。
|
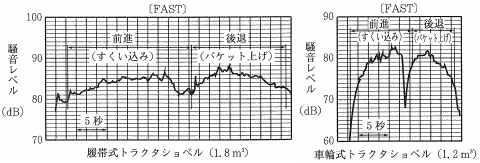
図2-2 ローダ作業の騒音レベル波形
|
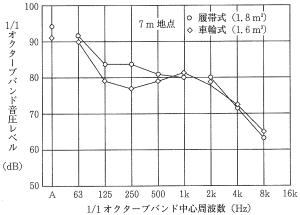
図2-3 ローダ作業騒音の周波数特性
|
|
b) 振 動
ローダ作業時の振動レベル例を図2-4に示します。 当然のことながら、車輪式の方が振動レベルは低くなります。
|
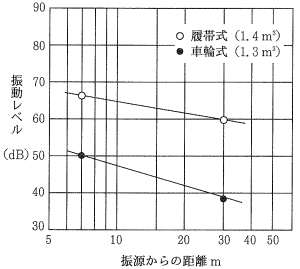
図2-4 ローダ作業振動と距離減衰
|
|
|
- バックホウ(油圧ショベル)
a) 騒 音
バックホウ(油圧ショベル)の主な騒音源は、エンジン関連と油圧系統で、通常はエンジン関連騒音が支配的です。 そして、バックホウの騒音は図3-1のような騒音源から成っています。
バックホウの作業騒音は、過負荷でリリーフ弁の作動時の騒音が短時間ですが最も大きくなります。 次いで通常作業時の音、ハイアイドル時の騒音です。 両者は殆ど同じ位のレベルですが、リリーフ時とハイアイドル時の騒音レベルの差は2〜4dB程度です。
|
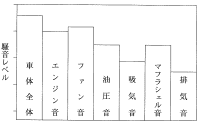
図 3-1 バックホウの騒音構成源
|
バックホウ(油圧ショベル)は、早くから低騒音化に取組まれ、都市土木でよく使われる0.8m3(104kW)級以下のものは、図3-1のようにハイアイドル時で70dB(A)を下回るものが殆どです。
実際の作業騒音の測定例では、図3-2のように7m地点で70〜85dB(A)とかなりな幅があります。
低騒音型バックホウ
 低騒音型バックホウは、作業騒音も従来機より小さくなっていることが判ります。 低騒音型バックホウは、作業騒音も従来機より小さくなっていることが判ります。
住宅に近接してよく使われる低騒音型ミニバックホウになると、図3-3のように70dB(A)を大幅に下回るものが殆どです。
|
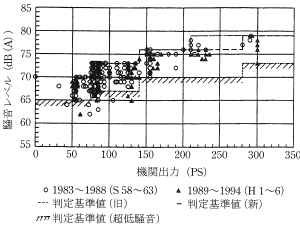
図 3-1 低騒音型バックホウの騒音測定例
(エンジンハイアイドル時の7m地点)
|
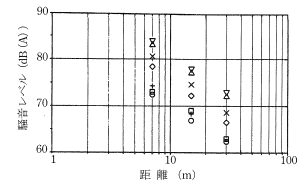
◇165PS級 低
▽150PS級 従 +150PS級 低
△120PS級 従 □77PS級 低
×62PS級 従 ○62PS級 低
図 3-2 バックホウの作業騒音測定例
|
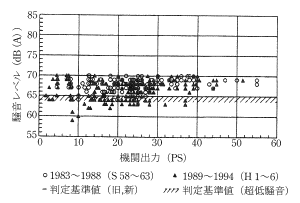
図 3-3 低騒音型ミニバックホウの騒音測定例
(エンジンハイアイドル時の7m地点)
|
騒音の周波数成分としては、機械に起因するエンジン音の低周波域が卓越し、作業に起因するものは高周波を含む広域のスペクトル構成となっています。
図3-4にバックホウの作業騒音の周波数特性(オクターブバンド)の例を示します。 0.45m3級バックホウの対策型と非対策型を比較していますが、全帯域で5dB前後の低減が成されているのが分かります。 また、このような波形はディーゼルエンジンの騒音の周波数特性によくみられ、125Hz帯域のピークはエンジン回転に依存する排気の周波数と考えられます。
|
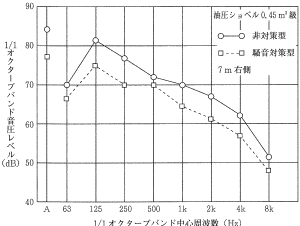
図 3-4 バックホウの作業騒音の周波数特性
|
b) 振 動
バックホウの振動は、掘削作業に伴うものが主です。
図3-5は0.8m3バックホウの振動を調べた例です。 掘削時の振動は5m地点でも70dB程度ですが、バケットを落下させると80dB以上の振動が発生しています。
振動対策が求められる場所での硬い地盤の掘削は、機種変更等の対策が求められます。
|
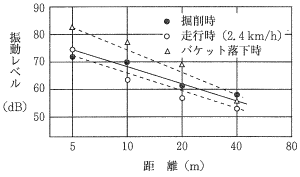
図 3-5 0.8m3バックホウの振動レベルと距離減衰
|
低振動型バックホウ
 低振動型のバックホウは、4社から0.8m3級5機種と0.5m3級の3機種が低振動型建設機械として指定を受けています。 低振動型のバックホウは、4社から0.8m3級5機種と0.5m3級の3機種が低振動型建設機械として指定を受けています。
バックホウの振動は、アタッチメントの急作動時に伴う機体の揺動によるものが大きいので、その対策を行っています。
低減策としては、油圧シリンダにクッション機構(or ショックレス機構)を備えています。
低減機構は、ストロークエンドのショック低減、つまり、作業時に本体振動が大きくなる油圧シリンダの作動末端部分の衝撃を減らすように作動速度を遅らせます。
制御系は電気パイロット方式と電子制御方式等があります。
下記のような効果が認められますが、サイクルタイムの増大、製造コストアップ等から実用的でないと見なされ、いずれも試作的に1996〜2000年に造られたのみで、現在は生産されていません。
参考に、低振動型0.8m3級(旧JIS表記0.7m3)バックホウの効果を調べた例を図3-6に示します。 各作業モード毎に振動対策機構のスイッチのOn/Offで比較しています。
作動時は、いずれのモードにおいても判定基準の55dBを下回っています。
|
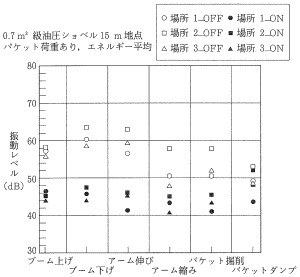
図 3-6 低振動型バックホウの振動レベルの例
|
|
|
- ダンプトラック
a) 騒 音
土運搬によく使われる11t ダンプトラックの走行速度と速度段毎の騒音レベルの関係を図4-1に示します。
発進時のギアシフトと騒音レベルの関係を通常発進と急速発進で比べてみると、図4-2のようにギヤシフトを遅らすことによる騒音レベルの増加量が掴めます。
|
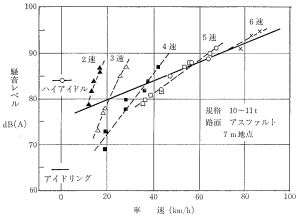
図4-1 ダンプトラックの騒音レベルと走行速度
|
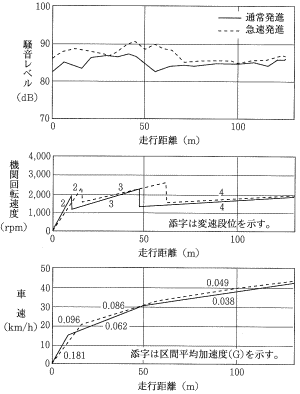
図4-2 11tトラックの発進パターンと騒音レベル
|
トラックのサイズ(最大積載量)別の定常走行時の車速と騒音レベルの関係を図4-3に示します。 騒音レベルは車速に比例し、10km/h毎に2〜3dB(A)大きくなっています。
|
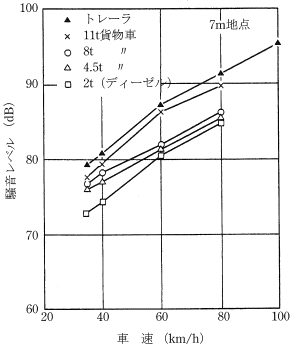
図4-3 定常走行速度と騒音レベルの関係
|
一般公道(舗装路)走行における10t・11t ダンプトラックの騒音レベルを図4-4に示します。 条件は、平均走行速度が30km/hで、通行量19台/100min、実車と空車が混在して通行しています。 測定距離が2倍になったときの騒音レベル最大値の減衰量は約7dB(A)となっています。
図4-5は、現場内盛土の未舗装走行における10t・11tダンプトラックの周波数特性(1/3オクターブバンド)の測定例です。
|
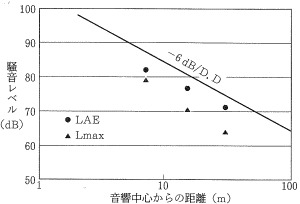
10t,11tダンプトラックの実車・空車混在
通行量:19台/100min、 平均走行速度:30km/h
図4-4 ダンプトラック場外走行の騒音レベル
|
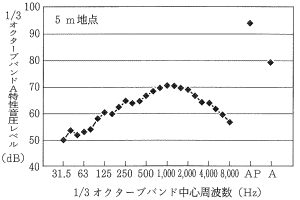
図4-5 ダンプトラック場内走行騒音の周波数特性
|
図4-6は、32tダンプトラック(HD320-2)の騒音レベルの距離減衰です。
図4-7は、32tダンプトラックの騒音の周波数特性です。 データは以下の機種と条件によるものです。
▲769B 実車
△769B 空車
●HD320-2 空車、60km走行時
○HD320-2 空車、加速時
|
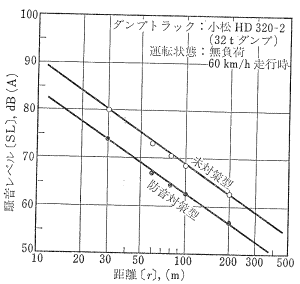
図4-6 32tダンプトラックの騒音レベル(距離減衰)
|
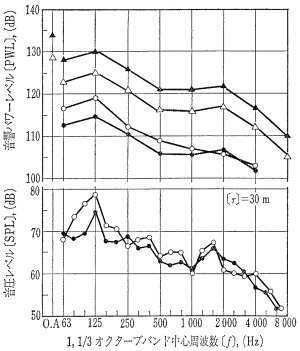
図4-7 32tダンプトラックの周波数特性
|
図4-8は、道路の縦断勾配の違いによろ騒音レベルの差を大型車と小型車で調べたものです。
勾配が5%変わると騒音レベルが約3dB増加しています。この値はHRB(Highway Research Board)が示していますトラック類の勾配による騒音レベルの補正値とも合致しています。
|
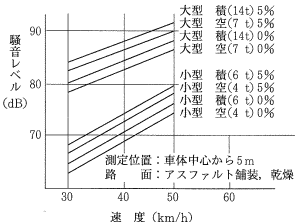
図4-8 道路勾配と騒音レベル
|
b) 振 動
10tダンプトラック走行時の振動測定例を未舗装路、舗装路について図4-9、4-10に示します。 これらは複数の現場の測定値によるものです。
曲線は、5m地点における振動レベルを基準点振動レベルとして、環境アセスメントに基づく建設機械の稼働に係わる予測式から求めています。
基準点振動レベルの値は、場内と場外では12dB程の差が出ていますが、これは場内の未舗装路に対し、場外は舗装路で剛性が高く平坦性も良好なためと思われます。
|
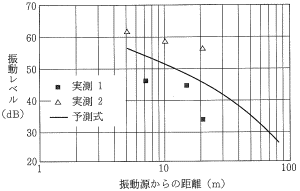
図4-9 10t ダンプトラック場内(未舗装)走行の振動レベル
|
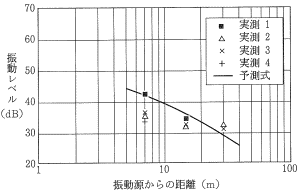
図4-10 10t ダンプトラック場外舗装路走行の振動レベル
|
図4-11は、路面状態と積載量の違いによる振動レベルの変化を散水車を試験車両として測定したものです。
路面状態毎の走行速度、積載量の増加による振動レベルの変化が分かります。
|
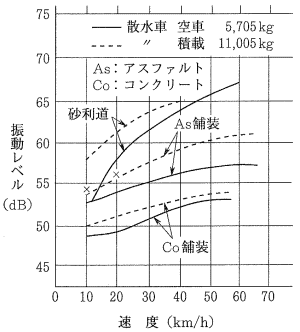
図4-11 路面と振動レベル
|
- 不整地走行車(クローラキャリア)
(株)諸岡がゴムクローラを装着した不整地走行車を開発してから、不整地走行車(クローラキャリア)を軟弱地や急勾配地で用いることが多くなりました。
図5-1に、クローラキャリアのエンジン出力と騒音レベルの関係を、四方向7m地点での平均ハイアイドル騒音レベルで示します。
走行時の騒音レベルは、ハイアイドル騒音より1〜2dB程度しか上がりません。 これはゴムクローラ装着と最高速度が10〜12km/h程度のためです。
|
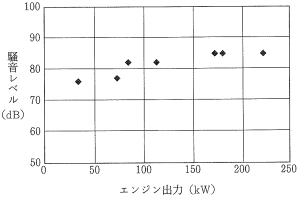
図5-1 クローラキャリアの騒音レベル
|
参考文献:「建設工事における環境保全技術」JGS
「地域の音環境計画」日本騒音制御工学会
「地域の環境振動」日本騒音制御工学会
「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック」JCMA
「建設作業振動対策マニュアル」JCMA
「建設工事における騒音・振動・粉じんの防止対策」原田,横田 |
|
 土工教室/環境/騒音・振動 土工教室/環境/騒音・振動    |