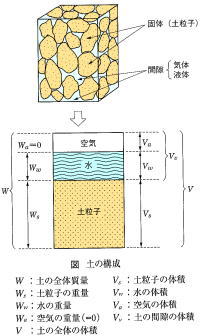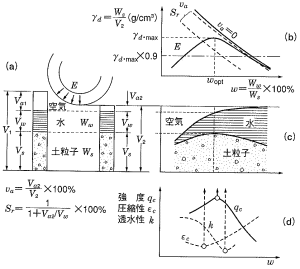3-5 締 固 め (初級編) 3-5 締 固 め (初級編) |
||||||||
| 3-5-1 土の締固め原理 |
||||||||
|
||||||||
3-5-2 締固め機械の種類 締固め機械を分類するとローラ系と平板式に大別でき、一般的に下のような系統に分類されている。 さらにこれらは、自走式、牽引式、重量等によっても細分される。 |
||||||||
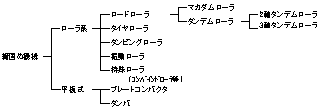 図-3 締固め機械の分類 |
||||||||
| 現在国内で使われている主な締固め機械を以下に示す。 大規模盛土で用いられる締固め機械は、大型振動ローラ、タンピングローラ、タイヤローラ、ブルドーザ等がよく使われ、牽引式は姿を消しつつある。 小規模な埋戻し・裏込めでは、ハンドガイド式振動ローラやタンパ、プレートコンパクタが使われる。 |
||||||||
 図-4 締固め機械 |
||||||||
(1) 振動ローラ (フラットロール) フラットロールを装着した土工用の振動ローラ、砂質土に適する。 土砂用は通常11t級が用いられ、ロックフィルでは16t級以上で締固める。 (2) 振動ローラ (タンピングロール) タンピングロールを装着した土工用の振動ローラで、粘性土や泥岩の締固めに適する。 この振動式のタンピングローラは1980年代に登場した。 (3) タイヤローラ タイヤローラは、空気タイヤの特性を活かして締固めを効果的に行うもので、路床・路盤の転圧からアスファルト混合物舗装や表層転圧まで幅広く利用されている。 また、水タンクによるバラスト荷重調整が可能で、粘性土、砂質土、軟岩等さまざまな土質に適応できる。 国交省の積算上の標準締固め機である。 (4) 自走式タンピングローラ タンピングローラは、フートの貫入・攪拌により間隙水を消散させる。 フート先端に荷重を集中させて土塊を破砕でき、土丹等のスレーキング性軟岩の破砕・締固めに有効である。 フィルダムのコア締固め等によく用いられる。 (5) コンバインドローラ 鉄輪(振動輪を含む)とタイヤローラを組合せた複合ローラ (6) マカダムローラ ロードローラの一種で、三輪の舗装用締固めローラ (7) ハンドガイドローラ Walk Behind ハンドガイド式の小型振動ローラ、自重600〜800kg級が一般的で、2軸の鉄輪で、全輪振動・全輪駆動式が多い。 構造物の埋戻し等、狭いエリアの締固めに利用する。 (8) タンパ/ランマ ハンドガイド式の締固め機で、上部に搭載したエンジンの回転力をクランク機構によって往復(上下)運動に変換して、器械下部の打撃版に伝達する。 間にスプリングを咬まし、上下運動を増幅させる。 構造物の埋戻し等、狭いエリアの締固めに適する。 (9) プレートコンパクタ(振動コンパクタ) ハンドガイドによるプレート式の振動締固め機、これは起振機を平板の上に搭載し、偏心軸を高速回転させて遠心力を発生させて、その振動により締固めと自走を同時に行うものである。 構造物の埋戻し等で、ローラが入れない狭いエリアの締固めに利用するが、締固め力は弱いので薄層で締固める。 |
||||||||
| 3-5-3 締固め機械の選定 締固め機械の選定には、締固め仕様、土質条件、施工規模等の施工条件を考慮して決定する。 選定の目安として下表が参考になるが、大規模盛土の場合は試験施工を実施して、最適な機種の検証を行う。 |
||||||||
表-1 締固め機械の選定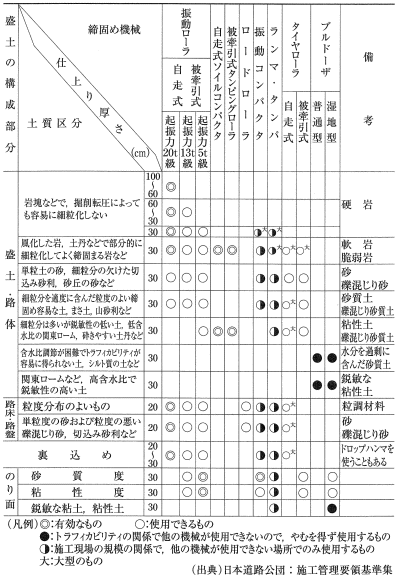 |
||||||||
| 3-5-4 情報化施工 下図は、締固め機械にRTK-GPS受信機やTS用ターゲットを搭載して、ローラの走行軌跡を記録して緻密な転圧回数管理を行うシステムで、大規模土工の締固め管理法として一般化しつつある。 また、敷均ブルドーザも同様の技術を用いて、撒出し厚の管理に利用している。 |
||||||||
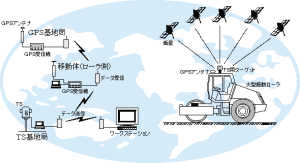 図-5 情報化施工 :GPSやTSを用いた締固め管理 |
||||||||
→ 締固め作業の施工写真 → 締固め(気液放散)整形技術.pdf.1.26M → 盛 土.pdf.483k |
||||||||
|
|
||||||||