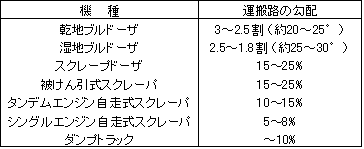機械土工の基本の項で概説しましたように、重機土工は、 スクレーパ工法と ショベル& ダンプトラック工法に大別でき、機種によって作業の適用範囲が違ってきます。
図-1に、それら組合せ機械の基本型と機種毎の作業の適用範囲を示します。
それぞれの作業における機械の選定は、施工性の観点に主眼を置いて検討します。 それぞれの作業の施工性とは、掘削性・積込性・運搬性・締固め性となります。
- 掘 削 : 掘削性 Excavatability
- 積 込 : 積込性 Loadability
- 運 搬 : 運搬性 Haulability
- 締固め : 締固め性 Compactability
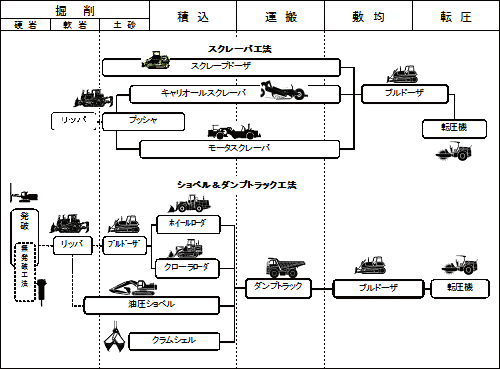
図-1 組合せ機械と作業範囲
3-1 運 搬
機械土工は、土の運搬がメインなので、運搬機の運搬性から検討します。
まず、運搬機の基本的な走行特性として、経済的な運搬距離の適用範囲を考慮します。
次に、トラフィカビリティの適否、更に走路に勾配がある場合は、登坂力・制動力を検討いたします。
3-1-1 経済的な運搬距離:
機種別の搬土距離の適合範囲は、「道路土工要綱」では図-2のように示しています。
より正確な搬土距離の適用には、投入機種同士で比較します。
投入各機種間の経済性の分岐点は、図-3のように機種毎のコストカーブ(運搬距離別施工単価)を描くことによって求めることができます。
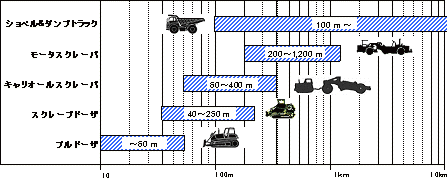
図-2 般土機械の適用範囲 (道路土工要綱)
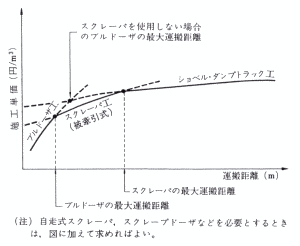
図-3 経済的運搬距離の分岐点
3-1-2 トラフィカビリティ:
走行性の検討では、搬土距離の他にトラフィカビリティが重要となります。
トラフィカビリティとは、重機の軟弱地等での走破性のことです。
土工機械が軟弱地を走行する場合、土質や含水比によって走行性が大きく変わります。 特に高含水比粘性土では、走行に伴うこね返しによって、土の強度が低下し、走行不能(カメ)になることがあります。
一般にトラフィカビリティを評価する指標としては、コーンペネトロメータで計測したコーン指数qcを用います。
表-1は、「道路土工要綱」に示されているコーン指数値で、機種別に、同一轍(わだち)を数回走行するのに必要なコーン指数を示しています。
但し、データが古いので、現行機種に合致しないものがあります。 特に、スクレープドーザの接地圧データは、かなり古く、SR40とSR264のものです。 また、超湿地型スクレープドーザ(SR40の超湿地型)は現存しません。
スクレープドーザは現在生産中止していますが、残存2機種のSR280(8m3)の接地圧は、空車で57〜60kPa、実車で83〜87kPaです。
スクレーパも古い小型機種のみなので、補足資料として図-4を添付します。
図-4の超ワイド低圧タイヤ付被けん引式スクレーパは、21t級湿地トラクタけん引の12m3(平積)スクレーパ(SBW15)です。
なお、けん引式スクレーパもバブル崩壊以降、生産がされていません。 モータスクレーパも輸入機が残っているのみで、国内から姿を消しつつあります。
→ トラフィカビリティの詳細(中級)
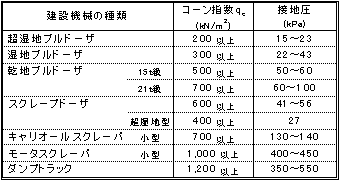
図-4 スクレーパのトラフィカビリティ
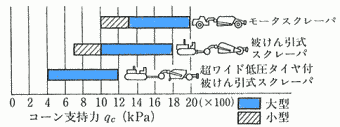
搬土機械の登坂力は、けん引力と車両総質量で決まり、上り坂で急激に速度が低下します。 また、降坂時には制動力(ブレーキ性能)が走行速度を決定します。
ブルドーザやスクレーパは、ブレードやボウルを制動に利用できますが、通常の走行勾配を表-2に示します。