2-1 運土形態:
土工事の運土の形態には、「線土工」と「面土工」があり、道路・鉄道・堤防工事のような線状の運土工は、線土工といいます。 また、宅地造成や敷地造成の多くは面状の運土工となるので、面土工と称します。
線土工と面土工には、それぞれに適した土量計算法と土量配分法があります。
2-2 土量計算法:
土量計算法は、線土工では線状の土量を捉えやすい平均断面法を用います。
面土工では、面状の土量把握に適したメッシュ法(柱状法)が適しています。
図-1は、平均断面法と柱状法の概念的な違いを示した模式図です。
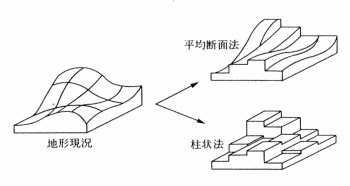
図-1 土量計算法
土砂は地山の状態から掘削すると、ほぐした状態(ルーズ状態)となり体積が増加します。
運搬中はルーズ状態で、盛場で締固めると体積が減ります(図-2)。
この変化率は土質によって異なりますが、参考に国土交通省で用いられている土質別の標準値を表-1に示します。
土工機械の作業能力を算定する際には、この変化率を用いて土量換算を行います。
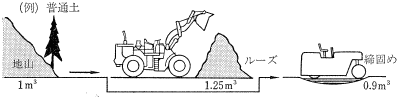
図-2 土量の変化
表-1 土の変化率(標準値)
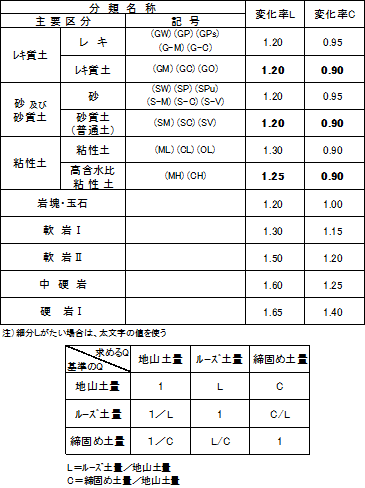
2-4 土量配分計画と配分法
2-4-1 線土工とマスカーブ:
道路工事等の線土工では、マスカーブ(土積図)を利用すると簡便で合理的な土量配分計画を作成できます。
線土工の土量配分では、まず、横断方向の切盛を行い、残りの過不足の土量を図-5のように縦断方向へ運搬すると考えます。 つまり、横断図において[切土量−盛土量]が+ならば、余った土量を縦断方向の近くの不足箇所に運び、マイナスで不足ならば近傍の余剰土を運んで来ます。
このような土量配分を山谷毎に土量集計して、配分の試行錯誤を繰り返すのでは非常に煩雑となりますが、累加土量曲線(マスカーブ)を用いて図式的に解くと合理的に配分できます。
マスカーブは土量のバランス区間を示しています。 従って、土量のバランスを示す平衡線を上下させるだけで、切盛のバランス区間を自在に変更でき、客土や捨土の調整区間の設定が容易に行えます。
表-2は、マスカーブを求めるための計算表です。 平均断面法による土量計算から累加土量を求めています。 この累加土量をグラフにプロットするとマスカーブとなります。
マスカーブには地山補正と盛土補正があり、表-2は地山補正の例です。
土質が2種類以上ある場合は、盛土補正が便利です。
詳細 → 土量配分計画 pdf.543kB
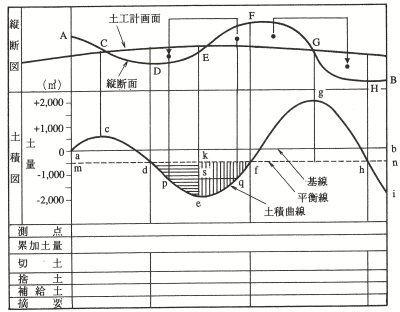
図-3 マスカーブ
表-2 累加土量計算
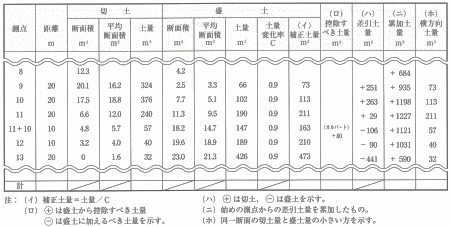
2-4-2 面土工の土量配分:
面土工の土量配分は、一般的に設計図にコンピュータで計算した最適土量配分計画を、図-4のような運土矢線図に示しています。 しかし、通常、運土矢線は直線最短距離で結ばれているだけで、施工性を考慮していません。 このため実施工においては、実際の運土経路を設定して、再計画する必要があります。
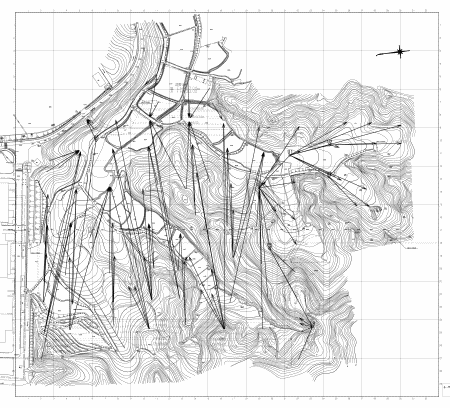
図-4 土量配分図 (運土矢線図)
2-5 工事用運搬道路
搬土機械のサイクルタイムは、工事用運搬道路によってほぼ決定します。 従って、運搬道路の巧拙が工事の死命を決すると云ってもよいほどです。
線土工において搬土経路はほぼ確定的ですが、面土工では線形設定が重要となります。
運搬走路の線形設定は、土量配分計画を基に土取場と盛場の空間的位置関係から地形、設計速度を勘案して縦断勾配、曲率、視距に配慮して計画します。
縦断勾配は、幹線では10%以下、支線でも15%以下の設定が原則です。
曲率半径は幹線で50m、支線でも30m以内とします。
また、工事用道路の幅員は、一般的な10tダンプトラックでは、8〜9m程度あればよいですが、大規模土工で重ダンプやスクレーパを使う場合は、運搬車両の車幅に応じた幅員が必要です。 安全上、最大車幅の3.5倍以上が必要とされています。
もし、3.5倍の幅員がとれない場合は計画速度を落とす必要があります。
詳細 →工事用道路の設計.pdf 781kB
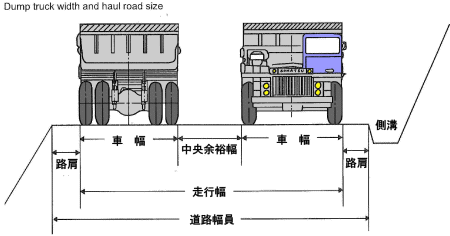
図-5 工事用運搬道路