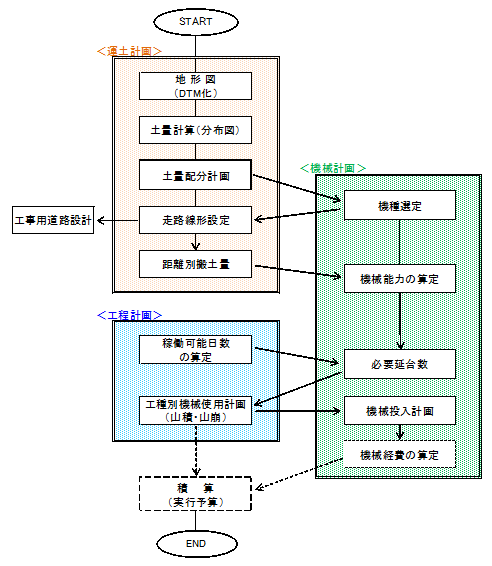1.施工計画の概要
1-1 機械土工の基本
機械土工は、切盛に伴う連続したダイナミックな作業であり、図-1のように掘削・積込・運搬・敷均・転圧からなる繰返し作業となります。 そこで、それぞれの作業に適した機械を選定して組合せることが重要となります。
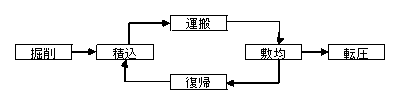
図-1 機械土工
図-2に、それら組合せ機械の基本型と機種毎の作業の適用範囲を示します。
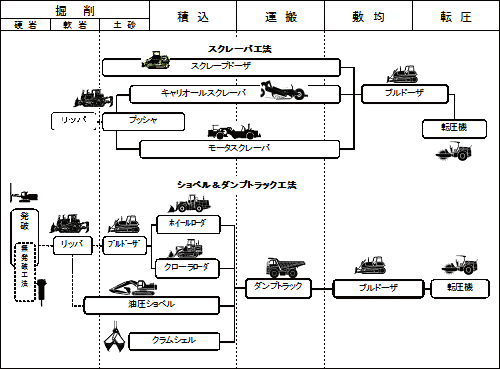
図-2 組合せ機械と作業範囲
スクレーパ工法の掘削は、図-3のようにダウンヒルカット工法で行います。
スクレーパ系の機械は、掘削・積込・運搬・敷均の土工作業サイクルを1台でこなせる自己完結的な機械で、スクレープドーザ、キャリオールスクレ-パ、モータスクレーパがあります。 組合せる敷均ブルは、補助的な端掻き(はなかき)程度で済みます。
モータスクレーパとキャリオールスクレ-パの積込みは、大規模土工では積込みサイクル短縮のために、原則としてプッシャを付けます。
ショベル&ダンプトラック工法の掘削は、図-4のようなベンチカット工法で行います。
ショベル&ダンプトラック工法の積込機は、油圧バックホウが主流ですが、必要に応じて、ホイールローダ、クローラローダ、クラムシェルを選択します。
バックホウは掘削・積込み能力がありますが、ローダ系は掘削力がないので、切崩しのブルドーザを必要とします。
また、ダンプトラックは、敷均し能力がないので、敷均しブルが必須となります。
岩掘削においては、軟岩はリッパ、硬岩は発破による掘削が基本です。 しかし、発破が制限される場所では、ブレーカ等の無発破工法が採用されます。
また、発破等で破砕した硬岩の運搬は、基本的にダンプトラックで行います。
スクレーパ系では、積込みに難があり、タイヤカットのリスクもあります。
特にモータスクレーパは積込み時に駆動輪に負荷をかけるとタイヤが切れるので、プッシャだけの力で積込む必要があります。
1-2 施工計画の概要
機械土工は、通常、上記の組合せ機械を使って計画します。 そして、施工計画の立案は、計画者が施工の展開を頭の中でイメージして組立てるものです。
施工計画は、概ね図-5のような手順で作成します。
まず、土量計算を行い、土量分布を把握してから、運土計画(土量配分計画)を作成します。
土量配分が決定しますと、搬土経路を設定して、土質別の搬土距離を求め、これ等を作業単位(工種)として、機械計画を立てます。
機械計画では、これらの工種に適した組合せ機械を選定し、それぞれの機械能力計算を行い、工種別に必要延べ台数を求めます。
この機種選定の際には、特に地形(勾配、運搬距離等)と土質との適性を考慮します。
続けて、機械を工程表の時間軸に割り振って、実際の投入台数と投入時期を決定します。
最後に機械経費等を積算し、見積書や実効予算書を仕上げます。